
お電話にてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
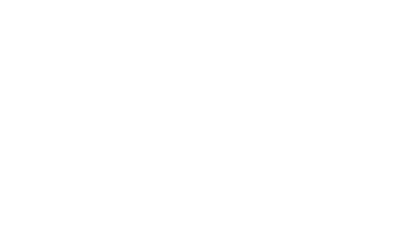
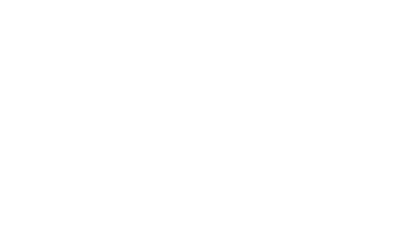
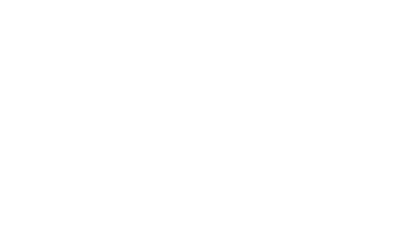
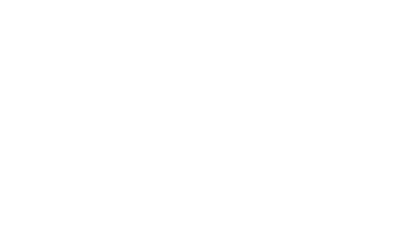
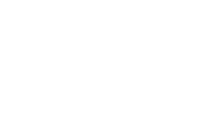
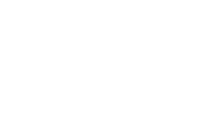
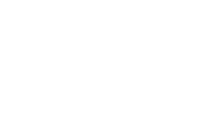
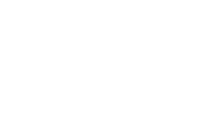
| 住所 |
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2丁目18-10 |
|---|---|
| アクセス | JR日暮里駅徒歩1分 |
| 電話 | 03-5615-2388(フリーダイヤル:0120-168-468) |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日【年末年始休業】12/27(水)~1/3(水) |
| 駐車場 | なし |
| 許可証 | 千葉県公安委員会許可 第441370000662号 |
| その他の情報 | その他の情報は、特定商法に基づく表記をご覧ください。 |
2022年9月、古美術品・骨董品、貴金属や宝飾品の買取専門店『くらや日暮里店』がNEWオープン。
JR日暮里駅東口より、日暮里舎人ライナー尾久橋通り口のエレベーターを降りてすぐの路面店です。
ご自宅の押し入れや箪笥、蔵、物置の中に、価値のわからない骨董品が眠っていませんか?
『くらや日暮里店』は、掛け軸や現代アートをはじめ、茶道具・書道具といったお道具類、日本刀や鎧などの武具、人間国宝作家・現代工芸作家が手掛けた作品などの査定・鑑定を行っております。外国の旧金貨や切手、古紙幣・古銭類、貴金属やブランド品など幅広いジャンルの買取も可能です。
遺品整理や生前整理、引っ越し前の処分や旧家の片付けなど、古いものを整理する機会は増えています。
そのような場面こそ、価値のある古物を見極める鑑定眼は重要です。
どんなものにどんな価値が有り、なぜその価値になるのかをしっかりとお伝えすることも、当店ができる整理のお手伝いの一部と考えております。
「古いものだし捨ててしまおうか…」「大切にしてきたものだから価値の分かる人に使ってほしい」など、処分の仕方にお困りの方は是非一度ご連絡ください。専門的な知識を持つ経験豊富なプロの鑑定士が、財産の価値を見極めながら適正な価格を見いだし買取します。
店頭での買取はもちろん、出張買取にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
買取品目
買取実績



準備中になります。












絵画には「タトウ箱」や「黄袋」が付属していることがあります。また人気作家の作品では発売時に作品証明書が発行されていることがあります。購入時の付属品が一緒にあることで査定金額UPにつながります。 掛軸の場合、近現代の作家のものだと「共箱」に収まっている方が査定が高くなります。江戸時代の古画ではこの共箱がありませんが、代々家に伝わってきたものだと古い伝世の箱やお蔵の中で大事にされてきたものだと蔵番札が付いていることがあります。いづれも時代考証の役に立つものなので一緒にお持ち下さる方が良いと思います。 勿論、絵画や掛け軸では真贋が最も重要なポイントですが、古いものはではその様子もまた重要なポイントになります。 ※「タトウ箱」とは額縁などを収める箱で、作者や画廊のシール等貼られているものもあります。 ※「共箱」とは作家自身でその木箱に署名(箱書き)したものを指します。
一緒にお持ちいただけるとで査定額のアップが期待できるもの。
★箱
★作品証明書
茶道具、煎茶道具では箱に収まっているものは必ず箱と一緒にお持ちください。例えばお茶碗だと本体・共箱(その作品のための専用の木箱)・共布が揃っています。これは茶碗本体に作家の印(陶印)があり、箱には作家のサインと印があり、近年の工芸作家のものだと茶碗を包む布にも押印されています。 また書付のあるお道具は二重箱になっているものがあります。書付とは茶道の家元や高僧が作品の名前を書き記したもので「書付箱」といわれます。書付箱は茶碗・水指・棗・香合・茶杓や掛物などあらゆるお道具に存在します。
一緒にお持ちいただけるとで査定額のアップが期待できるもの。
★共箱、共布
★書付箱、二重箱
★誂えの良い古布に包まれている場合はそのままご一緒に
宝石やジュエリーでは、ダイヤモンドのグレーディングレポートや鑑別書、ブランドのギャランティ等の証明書や箱などの付属品が揃っている方が査定額のアップが期待できます。 宝石やジュエリーにもハイブランドの製品があります。箱やブティックの販売証などがあれば一緒にお持ちいただくことで高評価となります。 また、時計は箱と保証書も一緒にあれば査定額がアップします。購入時の付属品としてベルトの余りコマや取扱説明書などもあれば査定額のアップが期待できます。
一緒にお持ちいただけるとで査定額のアップが期待できるもの。
★ダイヤモンド → グレーディングレポート
★ジュエリー → 鑑別書や鑑定書
★ブランドジュエリー → 箱や保証書、ブティックの販売証明書
★時計 → 箱、保証書、ベルトの余りコマ、取扱説明書などの付属品
日本刀で一番重要なものは「登録証(銃砲刀剣類登録証)」です。 刀と登録証は必ず合っているものです。複数お持ちの方で刀と登録証が混ざってしまいどれがどれか判らなくなった場合はご相談下さい。 また鑑定書がある場合は、必ずお持ちください。査定金額のUPが期待できます。 鑑定書には新旧2種類があります。旧タイプのものは「貴重刀剣」「特別貴重刀剣」「甲種特別貴重刀剣」があり、新タイプのものは「保存刀剣」「特別保存刀剣」「重要刀剣」などがあります。 稀に古い古文書のようなもので極めが書かれた折紙が付属している刀もあります。
必ず一緒にお持ちいただくもの。
★登録証(銃砲刀剣類登録証)
一緒にお持ちいただけるとで査定額のアップが期待できるもの。
★鑑定書・・・貴重刀剣、特別貴重刀剣、甲種特別貴重刀剣、保存刀剣など。
★箱や伝来書、極め折紙、古くからあるものはそのまま一緒に。
ブランド品には「ギャランティカード」という各ブランドが品質を保証している保証書が付属しています。お使いになるなかで紛失されていることがありますが、あれば一緒にお持ちいただくことで査定額のアップが期待できます。また購入時には保存袋や外箱、ブティックの販売証などもありますので付属品として一緒にお持ちいただけると査定額にプラスされます。他にものブランドのノベルティがあれば更に査定額のアップが期待できます。
一緒にお持ちいただけるとで査定額のアップが期待できるもの。
★ギャランティカード
★保存袋や外箱
★ブランドのノベルティグッズ
有名百貨店では人間国宝や文化勲章受賞の作家、その当時に注目されていた作家や人気の高い作家の個展を行っていました。それぞれの作品には専用の木箱が用意され作品名や作家のサインが書かれています。これを「共箱」といいます。共箱は作品を運搬する際の保護にも必要ですし、作家直筆のサインもありますので価値のあるものです。 また、個展ではカタログが発行されていることが多く、もしあれば一緒にお持ちいただくことで査定額のアップが期待できます。
一緒にお持ちいただけるとで査定額のアップが期待できるもの。
★共箱、共布、解説書
★個展のカタログ
★百貨店の領収書や販売証など
買取専門店は、はじめてだったので緊張しました。価値があるのか全く分からず「二束三文だったら恥ずかしい」と思いながら連絡。買取方法を電話で相談できたので安心でした。中国で暮らした義父の遺品に、思った以上の価値があり驚きました。ありがとうございました。
昔、海外で買った貴金属を買取ってもらいました。とても安かったので「本物だよね?」と、疑ったのを覚えています。今、金が高いとは聞きましたが…。こんなに高く買ってもらえるとは、思いませんでした。デザインの古いネックレスや指輪が他にもあるので、また来ようと思います。
この版画は、父が購入しました。引っ越しを機に、飾る場所もないので売ることにしました。思っていたよりも高い金額で売却でき、とても満足しています。気さくなスタッフさんで、緊張や不安もなくお話ができました。また、相談させてください。
母の遺品の茶道具を買取してもらいました。木箱入りのお茶碗は、思った以上の金額で売れ驚きました。母も価値のわかる人に買ってもらえ、喜んでいると思います。店員さんの説明も丁寧で相談してよかったです。ありがとうございました。
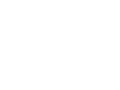
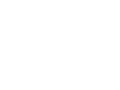
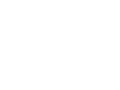
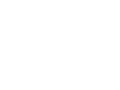
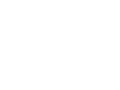
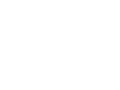
よくある質問
買取させて頂いたお品物の返品は、誠に申し訳ございませんがお受けできません。
キャンセル料金は頂いておりません、お気軽にご相談ください。
対応致します。ご連絡を頂ければ予定変更は可能ですのでお気軽にご連絡ください。
出張買取をさせて頂いたお品物はクーリングオフが適応致します。買取日から8日間以内にご連絡を頂ければ返品の対応を致します。
対応致します。お気軽にご相談ください。
対応致します。出張料金は無料ですので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
お電話にてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
営業時間:10:00~18:00
対応エリア
駅が入ります駅が入ります駅が入ります駅が入ります駅が入ります駅が入ります駅が入ります
東京都特別区に指定され、23区の東部に位置する荒川区。南千住や日暮里駅前地区には近代的な景観が誕生し、区内のほぼ真ん中を走る都電荒川線の周りにはどこか懐かしい街並みが広がっています。
荒川区は、発足した1932(昭和7)年から1945(昭和20)年頃にかけて都内で最も人口の多い区でした。隅田川沿いを中心に、衣服・皮革・自転車・鉛筆など生活に密着した製品を生産する町工場が集まり、発展していきました。
日暮里地区の歴史は古く、縄文・弥生時代の遺跡が発見されています。徳川家康が江戸に入府して間もない1594(文禄3)年に千住大橋が架橋され、日光街道が開通したことで賑わった南千住周辺にも、大名屋敷など多くの史跡を見ることができます。
日暮里・南千住に次いで古い歴史を持つ尾久周辺の地域は、古くから農村地区でした。大林院や宝蔵院など周辺の寺院には、鎌倉・室町時代に建立された板碑が伝えられています。
区内に多くの史跡をのこした〈太田道灌〉は、江戸城を築いたことで知られる人物です。日暮里駅前にある銅像をはじめ、南千住の石浜城跡、西日暮里の諏訪神社、道灌山、道灌丘碑などは太田道灌ゆかりの地ならでは。また、松尾芭蕉の〈奥の細道〉旅立ちの地としても縁深く、小林一茶や正岡子規など多くの文人が俳句を詠んでいます。
現在区内にはJR山手線・京浜東北・常磐線、東京メトロ千代田線・日比谷線、都電荒川線、日暮里・舎人ライナー、京成本線、つくばエクスプレス、成田スカイアクセス線の各線が走っています。充実した交通網の発達で都電路線が次々に廃止されていきましたが、その中で唯一残された〈荒川線〉は荒川区のシンボル的存在と言えるでしょう。
荒川区は〈繊維のまち〉としても有名です。JR日暮里駅から日暮里中央通りを中心に、90軒以上もの生地織物店が連なっており、ここで販売される服飾品はニポカジ(日暮里カジュアルの略)の名で親しまれています。 現在は工場跡地を活用した大規模な再開発が行われている荒川区。懐かしさの残る下町風情はそのままに、新しいまちづくりが進められています。
東京都23区のうち、最北端に位置する足立区。西は北区、南は荒川区と墨田区、東は葛飾区に囲まれており、北は埼玉県に面しています。 足立という地名は奈良時代に起源があり、645年に起こった大化の改新後に制定された〈武蔵国足立郡〉がその名の由来となっているのだそうです。奈良時代当時の足立郡は、現在の足立区と比べかなり広範囲に広がっていました。 足立区が発展したのは江戸時代のこと。徳川家3代将軍家光の時代には、千住が日光街道初の宿場となり、日光東照宮参詣や参勤交代の大名行列で大変な賑わいをみせます。江戸以北と江戸を繋ぐ街道は、その殆どが千住を経由するようになっていきました。 明治から大正にかけては工業も盛んになり、中でも煉瓦産業は足立区の主要産業でした。煉瓦産業が活発化した理由として、隅田川沿いの土壌が煉瓦造りに適していたこと、東京中心部へ運搬する際に隅田川の水運が便利だったことなどが挙げられます。煉瓦造りの本堂を持つ〈勝専寺〉は、区の文化財にこそ未登録ですが、千住の赤門寺として名高いです。
歴史と文化が色濃く残る〈西新井大師〉は、都内でも有数の観光地。神奈川の川崎大師、千葉の観福寺とならび〈関東厄除け三大師〉としても知られています。境内におかれた厳かな大本堂をはじめ、文化的にも価値の高い建造物が数多く存在します。
日暮里・舎人ライナーの舎人公園駅すぐの所に広がる都立〈舎人公園〉は、県境にもほど近い足立区北西部に位置する総合公園です。都立公園としては水元公園(葛飾区)、葛西臨海公園(江戸川区)に次ぎ、東京都23区内で3番目となる広さを誇ります。1981(昭和56)年の開園以降も順次整備が進められており、2021(令和3)年に完成した遊具エリア・冒険の丘は、子供たちを中心に人気を集めています。
荒川や綾瀬川、舎人公園など豊富な自然環境が点在し、西新井大師等に代表される多くの名所旧跡にも恵まれた足立区。現在では、西新井駅周辺地区や新田地区、千住大橋駅周辺地区などで再開発も進められており、更なる発展が期待されています。
東京都東部に位置し、千葉県・埼玉県にも接する葛飾区。東西には荒川・江戸川が、区内中央には中川が流れる、河川に囲まれた行政区です。他地域からの転入も多く、2022年現在では東京23区のうち9位となる人口を擁しています。 万葉集にも登場する葛飾という名は、古くからあるこの地域一帯の地名が由来です。発足当時の葛飾区役所は、現在の〈かつしかシンフォニーヒルズ〉が建っている場所にあり、夏になると蛍が飛ぶような田園が広がっていました。 奥戸周辺の地域には、古墳時代から中世にかけて集落が形成されていたようです。本郷遺跡・鬼塚遺跡からは、農耕用と推測される鋤や田下駄などが出土しています。鬼塚は葛飾区指定史跡で、神事が行われる場所であったと考えられています。 東京都が1998(平成10)年に指定史跡とした〈葛西城址〉は、葛飾区青戸にある名所旧跡です。
青戸にはかつて関東管領上杉氏が築いた葛西城があり、小田原北条氏によって攻め落とされ、徳川氏により再興されて以降は鷹狩の宿舎として使われていました。 水戸佐倉街道が通り、江戸と地方を結ぶ交通の要衝として発展した葛飾区は宿場町として栄えていました。河川が豊富なこともあり農業も盛んに行われていましたが、明治から大正期には工業地としても発展。昭和の高度成長期を経て減少傾向にあるものの、区内の工場数は現在でも都内トップクラスです。
緑豊かな〈堀切菖蒲園〉は、江戸時代後期頃から花菖蒲の名所として知られています。葛飾菖蒲まつりの際には、区内唯一の水郷景観を持つ〈水元公園〉と堀切菖蒲園の両会場にて、和太鼓や琴の演奏、民謡踊り、野点など様々なイベントが行われます。
葛飾区は、映画〈男はつらいよ〉や漫画〈こちら葛飾区亀有公園前派出所〉の舞台としても有名です。柴又駅前のフーテンの寅像や亀有駅前の両津勘吉像など、登場人物がモチーフとなった銅像が随所に設置されています。 映画や漫画のファンが多く訪れる都内有数の観光地・葛飾区は、再開発が進められながらも下町情緒が色濃く残された街です。
東京都の東部に位置する墨田区は、江戸の伝統や文化が息づくエリア。西から隅田川を区境とし、東は荒川と中川の河川に挟まれた町です。日本を代表するランドマークも多く。江戸情緒を残す下町付近には、東京スカイツリーがそびえ東京の大パノラマを堪能できます。
両国国技館では、日本の国技〈大相撲〉を開催。最大1万人を収容します。また、世界的に名高い葛飾北斎生誕の地として知られる墨田区には、すみだ北斎美術館も設置され訪れる観光客は後を絶ちません。 歴史を遡ると振袖火事をきっかけに、隅田川に両国橋が架かりました。現在の墨田区南部(本所)は武家屋敷の移転先に選ばれ、職人や商人も移り住みました。隅田川の運河や水を活かし、瓦・染め物・材木・鋳物など地場産業が発展。明治になると金属の玩具やガラス製造など工業地帯化が進みました。日用品や各種部品の生産も盛んになり、現在にいたります。
史跡も多く、赤穂浪士が討ち入りした吉良上野介屋敷跡の本所松坂町公園。慈覚大師によって建立された、本所の総鎮守の牛島神社。向島では向島百花園や桜餅で知られる長命寺や黄檗宗の弘福寺。江戸の情緒が感じられる代表的な庭園の旧安田庭園は、常陸国笠間藩主本庄因幡守宗資の下屋敷として築造され、東京都の名勝に指定されています。
ゆかりのある偉人には、江戸無血開城を成し遂げ倒幕の立役者である勝海舟、俳人の小林一茶や松尾芭蕉。羅生門で有名な作家の芥川龍之介や明治・大正の小説家の森鴎外など多く輩出。江戸期から庶民の行楽地として親しまれる隅田川一帯にに咲く桜は、将軍徳川吉宗が隅田堤に植えたことが始まりでした。現在の隅田川や荒川には臨海部を水上バスが運航し、隅田公園の千本桜を臨めることで人気です。吾妻橋から桜橋まで川岸1kmに渡って満開の桜が咲き誇ります。毎年開催される隅田川の花火大会も250年余りの伝統があり、東京の夏の夜空を彩る日本最古の花火大会です。
東京都の北東部に位置し、23区の中で最も小さい面積を持つ台東区。東京府東京市(のちの東京都)にかつて存在した下谷区と浅草区が合併し、1947(昭和22)年に誕生しました。
現在の千代田区や中央区などとならび、都内で最も古い市街地のひとつです。 台東区で発見された古代遺物の内容から、古墳時代の頃から有力者が支配していたことが推測されます。
江戸時代の遺跡としては、寛永寺旧境内の遺跡、都立白鴎高等学校の大名屋敷跡、池之端の寺院跡などが発掘されています。 1625(寛永2)年に建立した〈寛永寺〉は、京都の比叡山に倣ったお寺です。弁天堂が浮かぶ不忍池は、琵琶湖を模して造られています。現存する不忍池辯天堂は空襲により焼失するも、1958(昭和33)年に再建されました。
区内には多くの重要文化財が存在しますが、約1400年の歴史を持つ〈浅草寺〉は都内屈指の観光スポットです。入唐八家のひとり円仁をはじめ、平安時代後期の武将・源義朝、室町幕府の初代将軍・足利尊氏など、名だたる歴史の偉人達が浅草寺を訪れています。 桜の名所としても親しまれている〈谷中霊園〉には、およそ7,000基の墓があるのだとか。徳川家15代将軍慶喜、横山大観、渋沢栄一などが眠っていることでも知られています。
浅草橋・アメヤ横丁・かっぱ橋道具街通りなど、買い物客が訪れ賑わうスポットも豊富です。関東大震災や第二次世界大戦で甚大な被害を受けるも、浅草橋界隈の問屋街には大正・昭和初期頃の懐かしい街並みが残されています。
〈上野恩賜公園〉〈東京国立博物館〉〈東京芸術大学〉などが集結する上野の地域は、芸術と文化の発信地です。1872(明治5)年に創設された東京国立博物館は、国内で最も伝統のある博物館。日本のみならず、エジプトや西アジアなどの11万件を超える文化財が所蔵されています。 歴史・伝統・芸術など豊かな文化資源を有する台東区には、年間約4,000万人もの観光客や買い物客が訪れます。時代の流れとともに少しずつその姿を変えながらも、古き良き日本の下町文化が現在も根付いています。
東京23区のほぼ中心に位置する文京区。都心でありながら、自然が多く残されているエリアです。
坂道の多い区でもあり、名前がある坂だけでも115個存在します。主要駅は御茶ノ水駅や後楽園駅、水道橋駅です。
徳川家康によって江戸城下は発展し、屋敷や寺社仏閣が次々と建てられました。江戸中期の文京区内は中山道周辺に商家が多く建ち並び、商業活動も活発に行われました。
また、教育施設が江戸期から多く集まるエリアです。江戸期には、幕府の官学を学ぶ場の湯島の孔子廟。明治期になると東京大学など、誰もが知る機関が設立されました。 由緒ある建造物も数多く。国の重要文化財に指定される根津神社は、1900年の歴史を誇る神社です。多くの文豪にも愛されました。
五代将軍徳川綱吉が創建した護国寺は、武運長久を祈る祈願寺です。菅原道真が祀られる湯島天満宮は、毎年多くの受験生が足を運びます。随所に中国的趣向を凝らした回遊式築山泉水庭園の小石川後楽園は、水戸徳川家の上屋敷の庭でした。
関口にあるホテル椿山荘東京は、江戸期上総久留里藩主・黒田豊前守の下屋敷があった場所です。庭には有形文化財の三重塔があり、四季折々の景色を楽しめます。
文京区のシンボルといえば、東京ドームシティです。東京ドームや遊園地、ホテルやスパなどを合わせもつ総合的なレジャー施設として人気を博します。加えて、先鋭的な美術館や博物館、ギャラリーも多く有する文化の発信地です。
区内は、著名な文人・学者や政治家が多く。夏目漱石や森鴎外、宮沢賢治などが居を構えました。文人たちの生活拠点であったのと同時に、物語の舞台として多くの作品に登場します。夏目漱石の〈吾輩は猫である〉や樋口一葉の〈たけくらべ〉は、この地で生まれた作品です。文学作品に登場する坂には、森鴎外の小説の舞台となった鼠坂。夏目漱石の〈こころ〉では散歩の描写で、富坂などが登場しました。
豊島区は東京23区の北西部に位置し、新宿や渋谷と並ぶ東京三大副都心の池袋を擁します。特に池袋駅は、巨大ターミナルとして発展。JR東日本をはじめ、東武鉄道・西武鉄道・東京メトロと複数の路線が結集し、1日に平均約264万人が利用するといわれています。
周辺は百貨店などの商業施設や飲食店が建ち並び。池袋のランドマークとして知られるサンシャイン60の屋上には、日本初の都市型高層水族館のサンシャイン水族館を構えます。
また、日本初のマンション一体型の豊島区役所を、建築家の隈研吾氏が設計したのは有名です。
おばあちゃんの原宿で話題の巣鴨には、とげぬき地蔵の高岩寺があります。江戸期の巣鴨庚申堂(猿田彦大神)は、中山道の休憩所として賑わいました。
巣鴨は、江戸幕府15代将軍の徳川慶喜が住んでいたことでも知られています。 区の木にも指定されている桜のシメイヨシノは豊島区が発祥の地。神田川近くの氷川神社をはじめ、法明寺や染井霊園など区内には桜の名所が多くみられます。
他の草花では幕府とつながりのあった植木屋の伊藤伊兵衛がツツジを広めた地でもあり、JR駒込駅の土手に咲くツツジはその名残です。 かつて庶民が往来した中山道や鎌倉街道は、現在でも生活道路として利用されています。
都電荒川線〈鬼子母神前〉駅から〈面影橋〉駅へ続く道は、旧鎌倉街道の面影を残します。 目白にある目白庭園は都会の喧騒から離れ、自然と伝統文化が息づいた本格的な日本庭園です。
西池袋には、小説家・江戸川乱歩が46番目に見つけた土蔵付きの旧江戸川乱歩邸があり、ここで大ヒット作の怪人二十一面相が誕生しました。
雑司ヶ谷霊園は南池袋にあり、作家や音楽家など多くの著名人が眠る霊園です。小泉八雲や竹久夢二、夏目漱石、東條英機、東郷青児など著名人が眠ります。
江戸期には将軍の御用屋敷や鷹狩りのための御留場がありました。都心にありながらイチョウが立ち並び、自然を擁するこの霊園は人物の半生や歴史に思いを馳せながら、参拝される方も多いようです。
東京都の北部に位置し、埼玉県と隣接する北区。都心への利便性が高い一方、緑豊かな癒やしスポットが多い区です。
下町情緒のあふれる十条や自然の豊かな王子、高級住宅街の西ヶ原など地域によって違った表情を見せます。
区内を通るJRの駅数は11駅と最多を誇り、鉄道は赤羽に集中。昔ながらの路面電車の都電荒川線が通り、尾久車両センターや新幹線車両センターなど鉄道風景を楽しめます。
また、北区には桜の名所が幾つもあり、中でも都内屈指のスポットで知られるのは飛鳥山公園です。600本以上のソメイヨシノをはじめ、ウコンに関山とさまざまな桜が咲き誇ります。石神井川沿いの遊歩道も桜の名所のひとつです。
かつて、江戸の行楽地であり、日光へ続く日光御成道が通っていた北区。飛鳥山の花見や滝野川の避暑で賑わう様子が、歌川広重や勝川春潮の浮世絵にも残されています。
また、岩淵は交通の要衝でした。江戸期には、日光御成道の最初の宿場町として発展します。荒川の渡し場として水運も盛んだったこのエリアは、土地が低い地域性もあり多くの水害に遭遇。明治の大洪水を機に旧岩淵水門が建設され、荒川と隅田川の分岐点となりました。今では、東京都の歴史的建造物に選定されています。
北区の庭園といえば、大正初期の庭園の原型をとどめた旧古河庭園です。洋風・和風の庭園に石造りの洋館が見事に調和しています。また、赤レンガ図書館でお馴染みの十条にある北区中央図書館は、かつて弾丸製造工場として建てられました。 古くから王子に伝承される王子狐の行列は、誰もが知る伝統行事です。除夜の鐘とともにメイクやお面で狐に扮した和装束の人たちが、装束稲荷神社から王子稲荷神社までの1kmを練り歩きます。幻想的な行列を一目見ようと、国内外から観光客が訪れる一大イベントです。
ゆかりのある偉人では、芥川龍之介や北村西望、平塚らいてうをはじめ渋沢栄一や古河市兵衛が挙げられます。
山手線や京浜東北線、日暮里・舎人ライナーなど、複数の路線が交わる日暮里駅。山手線を使えば20分圏内で東京駅・上野駅・新宿駅・池袋駅へ移動でき、常磐線を利用すれば千葉県・茨城県にも一本で足を延ばすことができます。駅前にはバスターミナルもあり、浅草や錦糸町への移動も便利です。
日暮里駅東側には、大型複合施設〈サンマークシティ〉や高層マンションがそびえ、ビジネスホテルや飲食店も多くみられます。日暮里駅西側には昔ながらの情緒あふれる面影が残されており、〈谷中ぎんざ〉や〈谷中霊園〉などは散策スポットとしても人気です。食べ歩きも楽しめる谷中ぎんざは、戦前の下町風情が色濃く残る〈谷根千〉にあり、遠方から訪れる観光客で賑わっています。
駅北口から緩やかに上る、御殿坂の先にある〈夕やけだんだん〉も名所のひとつ。この階段に座り谷中銀座方向を見ると、綺麗な夕焼けを見ることができます。人気ドラマ〈ごくせん〉〈夢で逢いましょう〉〈野ブタ。をプロデュース〉などのロケ地として使われるなど、近年定番の撮影スポットです。
1日約2500本、20種類以上の列車が行き交う日暮里駅は、多種多様な電車を眺められるとして全国的にも知られています。日暮里駅の東西を結ぶ下御隠殿橋の中ほどには、〈トレインミュージアム〉というバルコニーが設置され、電車鑑賞を楽しむ人が多く訪れます。
駅前広場では、ブラスバンドによる音楽祭や各種イベントが開催されることも。毎月のように催される〈にっぽりマルシェ〉では、福島・宮城・熊本など全国各地の農産物や特産品が販売されます。
駅の南西にある千本鳥居で有名な〈根津神社〉は、約1900年の歴史を誇る鎮守社です。国の重要文化財に指定されている拝殿・唐門・透塀などは必見。東京十社のひとつに数えられる由緒正しい神社ですが、都内有数のツツジの名所としても知られています。
日暮里駅周辺は、江戸時代には庶民の行楽地として栄えていました。明治から平成にかけては様々な文化の発信地として発展し、現在は新旧の景観が共存する注目の地域です。
今から約50年前に開業した西日暮里駅は、山手線各駅の殆どが明治・大正時代に開業してきた中で、唯一昭和時代に誕生しました。
交差する営団地下鉄千代田線(現東京メトロ千代田線)との乗換駅として、国鉄に西日暮里駅がつくられたのは1971(昭和46)年。隣り合う日暮里駅とは僅か約500mしか離れていません。 西日暮里駅は、日暮里駅の北側に位置する駅です。本来なら北日暮里という名称の方が正しいように思えますが、1969(昭和44)年に先行開業した地下鉄の西日暮里駅にならい同じ駅名が付けられました。
駅ホームからは、道灌山通りと左右に立ち上がる切通しの断崖が見下ろせます。切通しの北側の台地が道灌山で、その一帯は全国屈指の進学校〈私立開成学園〉の敷地です。南側の台地には諏訪台が広がっており、〈諏方神社〉〈浄光寺〉などが点在しています。
西日暮里駅東口近辺は、居酒屋を中心とした飲食店が多く軒を連ねています。夜遅くまで賑わう繁華街と、閑静で歴史のある神社仏閣や学校施設が隣り合わせに共存しているのも、西日暮里駅の大きな特徴と言えるでしょう。
駅から徒歩数分という立地にある〈西日暮里公園〉の周辺は、江戸時代中頃より〈ひぐらしの里〉と呼ばれ、江戸近郊の行楽地として賑わっていました。
西日暮里公園の西下に建つ臨済宗〈青雲寺〉は、かつて花見の場所として賑わったことから〈花見寺〉とも呼ばれています。
西日暮里駅西口から谷中方面に向かってすぐの所に在る〈西日暮里富士見坂〉は、ドラマの撮影で使われたことも。周辺の壁が雰囲気のあるレンガ調で存在感を放ち、2004(平成16)年には関東の富士見百景にも選ばれています。
いくつもの路線が交差し、多くの人が行き交う交通の拠点、西日暮里。西日暮里駅が誕生してから約40年ぶりとなる2020(令和2)年に新駅〈高輪ゲートウェイ〉が開業したことから、この地域にも再び関心が寄せられています。
JR常磐線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレスが乗り入れる南千住駅。常磐線を使えば東京駅へ約15分、日比谷線なら銀座駅まで約20分で行くことができます。
2005(平成17)年のつくばエクスプレス開通を機に駅北東部が再開発され、ファミリー層を中心に人気を集めています。
南千住駅がある荒川区は、宿場町として栄えてきた歴史ある地域です。古くから水陸共通で交通の要となっている場所であり、大日本紡績(現ユニチカ)と鐘淵紡績(現クラシエ)の2大工場が立地する工業の町としても発展しました。
かつて南千住には、〈東京スタジアム〉という野球場がありました。千葉ロッテマリーンズの前身にあたる、毎日大映オリオンズが本拠地として使用していましたが、1972(昭和47)年限りで閉鎖。その後1977(昭和52)年に解体され、現在は体育館や軟式野球場などを有する〈荒川総合スポーツセンター〉が建てられています。
駅南側には山谷と呼ばれる地域があり、木賃宿が立ち並ぶ労務者の街としても有名でした。
1987(昭和6年)年以降は、南千住駅から旧汐入地区を中心とした大規模な再開発が始まり、〈LaLaテラス南千住〉〈BiVi南千住〉などといった複合商業施設をはじめ、高層マンションも複数建設されています。
隅田川と荒川が流れ、自然を堪能できるスポットが多いのもこのエリアならでは。隅田川沿いにある〈汐入公園〉には、子供達に人気の遊具やバーベキューが楽しめる広場もります。荒川区を4km(13駅)にわたり走る都電荒川線からは、時季により140種13,200株の薔薇を眺めることができます。 1950(昭和25)年開園の区立遊園地〈あらかわ遊園〉や、昭和の街並み再現や伝統工芸品が展示されている〈荒川ふるさと文化館〉、夏には隅田川花火大会の観覧場所になる荒川河川敷の〈虹の広場〉なども観光スポットです。 南千住駅周辺は、再開発による交通や生活の利便性と、昔ながらの東京下町の雰囲気を両得できる地域です。
JR常磐線で上野から2駅6分という、至便な地に位置する三河島駅。その開業は隣の日暮里駅と同じ1905(明治38)年と、歴史も古い駅です。日暮里駅・西日暮里駅へは徒歩での移動が可能で、東京23区内にあるJRの駅の中では5番目に乗車人員が少ないとされています。
一昔前までは老朽化した木造の建造物が立ち並び、駅前などは土地の有効活用が十分にされているとは言えませんでした。ところが1999(平成11)年に市街地再開発事業が立ち上がると一転、2014(平成26)年には地上34階、地下1階のタワーマンションが駅前南地区に竣工しました。
駅前北地区は、旧真土小学校の敷地を活用し、集合住宅・商業施設・体育施設などが一体で整備されていく予定です。飲食店や病院、薬局をはじめ、体育館やオープンスペースもつくられるようで、多様な世代が賑やかに行き交う駅前空間が生まれるでしょう。
京成電鉄本線の新三河島駅へは、徒歩10分未満で行くことができます。三河島駅との間にある北島商店(肉のきたじま)は、オリンピック水泳競技金メダリスト・北島康介選手の実家です。
三河島駅改札を出たところにある〈尾竹橋通り〉には、40以上の店舗が軒を連ねる〈親交睦商店街〉があり、その歴史は70年以上にもなるのだとか。駅の北東に広がる〈荒川仲町通り商店街〉には、500mほどの細い路地に八百屋・喫茶店・銭湯などが点在し、今も下町の雰囲気を残しています。
戦前よりコリアンタウンとしても栄え、安くて美味しい焼肉店のほか、本格的な韓国料理が味わえる店、韓国食材を扱う店などもあり、異国情緒が楽しめます。
駅の北側と南側では雰囲気ががらりと変わるのも、この地域ならではの特徴です。 周囲と調和するように、緩やかに変貌していく三河島駅周辺。日暮里や町屋といった人気エリアにも近く、再開発が進み利便性が増していることから、荒川区の穴場として注目されています。
隣接する都電荒川線の町屋駅前駅を含めると、計3路線が利用できる町屋駅。東京メトロ千代田線・直通で、大手町駅へは約13分、表参道駅へは約27分という立地です。京成本線も利用でき、成田空港へのアクセスも抜群です。
1931(昭和6)年、京成本線日暮里・青砥間開業と同時に設けられた町屋駅は、開業当時からの高架駅。千代田線が乗り入れを開始したのは、1969(昭和44)年のことでした。 町屋という地名の由来は諸説あるようですが、そのひとつに、良質な土が採れたことから真土野(まつちや)と呼ばれたものが転じて〈まちや〉になったという説があります。
町屋は古くから集落のあった肥沃な土地であり、弥生時代から人間の生活が営まれていたことが遺跡により証明されています。
江戸時代は江戸の近郊農村として発展し、三河島菜、三河島枝豆、荒木田大根などといった野菜の産地としても知られていたのだとか。現在の町屋は駅周辺が栄えていますが、元々の中心は慈眼寺などがある辺り。
今の町屋銀座の通りには、かつて江戸道が通っていたそうです。 町屋の中心となる〈尾竹橋通り〉の周りには、大小様々な商店街が連なっています。小売店や飲食店が立ち並ぶ〈町屋駅前銀座商店街〉、尾竹橋通り沿いに数百メートルに亘って続く〈まちやアベニュー〉、原稲荷神社に繋がる道として発展してきた〈いなり通り商店街〉などは、長く地元住民に親しまれてきました。
〈原稲荷神社〉は1590(天正18)年、徳川家康の江戸入府に伴い三河国(現愛知県)の百姓が町屋への移住を機に建立したとされる神社です。全国的にも珍しい阿弥陀三尊の線刻が施された庚申塔もあり、古くから町屋の人々に尊ばれてきたことが分かります。
歴史的スポットとは打って変わり、町屋駅から徒歩1分の所にある大型商業施設〈サンポップマチヤ〉も地元住民で賑わうスポットです。飲食店をはじめ、雑貨屋、アパレル店などが軒を連ね、休日には家族連れが多く訪れます。 隅田川沿いにはファミリー向けの大型マンションがずらりと建ち並ぶ一方で、古い飲食店も多く残る町屋駅周辺。町屋は、下町のどこか懐かしい雰囲気が残る街です。
東にはJR山手線の日暮里駅、北には西日暮里駅、西に東京メトロ千代田線の根津駅・千駄木駅。どの駅からも1km以内という徒歩圏に位置する台東区〈谷中〉は、隣接する荒川区・文京区との区境にあります。
近くには〈東京大学〉〈東京藝術大学〉〈日本医科大学〉などといった学芸の頂点に君臨する教育機関が点在しています。
江戸時代、寺町だった谷中は墓参りを兼ねた行楽地として栄えたそうです。
関東大震災や空襲を免れ、明治・大正・昭和の街並みが現在も色濃く残り、都内でもひと際特別な存在感を放ちます。
広大な敷地を持つ〈谷中霊園〉は、いわば都会のオアシス。谷中霊園には江戸幕府第15代将軍・徳川慶喜をはじめ、横山大観や渋沢栄一、鏑木清方、鳩山一郎などといった著名人が眠っています。
春は桜の名所としても親しまれる、都内屈指の散策スポットです。 上野恩賜公園の中に建つ〈東京国立博物館〉〈国立西洋美術館〉は、日本の芸術文化を世界に伝える発信地です。
また、ジャイアントパンダが名物の〈上野動物園〉や買い物からグルメまで楽しめる〈アメヤ横丁〉は、一年を通し多くの人で賑わいます。
最近メディアでもよく取り上げられる〈谷根千〉は、昭和の下町情緒溢れるエリアです。谷根千とは文京区から台東区の谷中・根津・千駄木を指す総称で、グルメの宝庫としてもその名を轟かせています。
千駄木周辺は、川端康成、森鴎外、高村光太郎、北原白秋など、多くの文豪が居を構えた歴史ある地域です。夏目漱石の〈吾輩は猫である〉は、東京市本郷区駒込千駄木町(現在の文京区向丘)にある家で執筆されました。
2016(平成28)年にインバウンド客を含め約300万人を集客し話題となった谷中地区。観光の目的として名所・旧跡巡りを挙げる声は多く、周辺地域の再開発が次々と進められる中で、谷中周辺の地域では建築物の保存再生や文化財の修復に注力されてきました。 寺と墓ばかりの古い町といったイメージを抱いたまま谷中を訪れると、その賑わいにきっと驚くことでしょう。今や谷中は、上野や浅草などといった東京観光のメッカに次ぎ、多くの人が足を運ぶ注目度の高い人気エリアです。